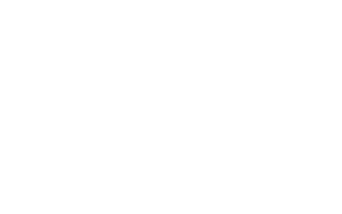共同研究開発契約の知財帰属完全ガイド:トラブル回避とモデル契約の活用法
お役立ち記事一覧に戻るオープンイノベーションを成功に導くためには、他社や大学との「共同研究開発」が不可欠です。しかし、新しい技術やアイデアが生まれる一方で、その成果である知的財産(知財)の帰属を巡るトラブルも少なくありません。特に「誰が権利を持つのか」「どうやって商用化するのか」といったルールを事前に決めておかなければ、せっかくの研究成果が塩漬けになったり、パートナーとの関係が悪化したりするリスクがあります。
この記事では、共同研究開発契約における知財の帰属や成果の取扱いについて、法務の観点から徹底解説します。特許法や著作権法などの基本原則から、共有特許権特有のリスク、そしてトラブルを未然に防ぐための契約条項のポイントまで、企業の開発担当者や研究者、法務・知財担当者の方が実務で使える知識をまとめました。経済産業省や特許庁が公開するモデル契約も参考に、オープンイノベーションを加速させるための契約戦略を学びましょう。
共同研究開発契約は、複数の企業や大学などが協力して研究開発を進める際に、その目的、役割分担、費用、そして最も重要な「成果の取扱い」などを定める契約です。オープンイノベーションの成功は、この契約の質にかかっていると言っても過過言ではありません。
Contents
共同研究の定義と法的性質

共同研究開発契約は、民法上の「準委任契約」の一種と解釈されるのが一般的です。民法第644条(受任者の義務)は受任者が善良な管理者の注意義務を負うことを、第656条(報酬・成果帰属)では委任の本質を規定しており、共同研究では当事者が互いに協力し、誠実に研究開発業務を遂行する基本義務が生じます(出典:民法第644条、第656条)。ただし、知的財産権の帰属や成果の取扱いに関しては、民法の準委任ルールより、共同研究開発契約に定める特約(契約による別段の定め)が最優先されます。
単なる業務委託と異なり、共同研究では各当事者が自身の持つ技術や知識、人材といったリソースを出し合います。目的は、単独では達成困難な革新的な成果を生み出すことです。そのため、契約では単に作業内容を定めるだけでなく、研究の過程で生まれる知的財産権の帰属や、成果物の利用条件を明確に合意しておくことが極めて重要になります。
知財帰属・成果扱いの重要性

なぜ、知財の帰属や成果の取扱いを厳密に定める必要があるのでしょうか。それは、ここでの曖昧さが将来の大きな紛争の火種となるからです。

共同研究の成果が出たはいいけれど、誰の特許になるの?うちの会社は自由に製品化できるのかな…?契約書を見返しても、なんだかハッキリしない…
例えば、以下のようなトラブルが考えられます。
- 権利の塩漬け: 共同で得た特許の権利(共有特許権)について、一方の当事者がライセンス許諾に反対し、製品化が進まない。
- 貢献度の対立:「発明への貢献度は自社の方が高いはずだ」と主張し、権利の持分割合を巡って争いになる。
- 予期せぬ競合: 共同研究の相手方が、得られた知見を基に競合製品を開発・販売してしまう。
こうした事態を避けるため、契約締結の段階で「誰が、何を、どのように使えるか」を具体的に定めておく必要があるのです。
知財帰属の基本ルール:特許法と著作権法の原則
共同研究の成果として生まれる知的財産の帰属を考える上で、まずは日本の法律における基本原則を理解しておく必要があります。ここでは、特に重要な「職務発明(特許)」と「職務著作(著作物)」について解説します。
職務発明の原始帰属(特許法第35条)

職務発明とは、従業員がその会社の業務範囲内で行った発明を指します。特許法では、この職務発明について以下のように定めています。
- 原則: 発明を完成させた「発明者(従業員)」に特許を受ける権利が帰属する(原始帰属)。
- 例外: 会社の勤務規則や個別の契約で事前に定めておくことにより、会社(使用者)に特許を受ける権利を直接帰属させることができる(出典:特許法第35条)。
**【Point】**
共同研究契約では、研究者個人ではなく、その研究者が所属する企業や大学などの「組織」が契約の当事者となります。そのため、研究から生まれた発明の権利は、まず職務発明のルールに基づき各組織に集約され、その上で、組織間で結んだ共同研究開発契約の条項に従って最終的な帰属(単独所有、共有など)が決定されます。
つまり、「個人の発明」と「共同研究の成果」は、別のルールで規律されると理解することが重要です。この点を混同すると、研究者個人が権利を主張し、組織間の合意が無効化されるといったトラブルに発展しかねません。大学等では個別規程により研究者個人帰属の可能性もあり、射程は組織規程依存となります。
職務著作の帰属基準(著作権法第15条・16条)

研究成果は、論文、報告書、ソースコード、データベースなど、著作物として保護されるものも多くあります。これら「職務著作」の権利帰属は、著作権法で定められています。
以下の要件をすべて満たす場合、契約などに別段の定めがなければ、著作権は会社(法人等)に帰属します(出典:著作権法第15条)。
- 法人等の発意に基づき作成されること
- その法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
- その法人等が自己の名義で公表するものであること
共同研究の場合、成果物(報告書など)を誰の名義で作成・公表するかが不明確なケースも多いため、著作権の帰属についても、共同研究開発契約で明確に合意しておくことが紛争予防につながります。
共同研究特有の成果管理:共有特許権と契約条項
共同研究から生まれた発明を、複数の当事者で共同出願すると「共有特許権」が発生します。この共有特許権は、単独で保有する特許権とは異なる特殊なルールがあり、その運用には注意が必要です。上記ルールは契約条項により変更可能であり、契約合意が法令に優先する(ただし法令の強行規定を除く)。
共有特許権の運用リスク(特許法第73条)

特許法第73条は、共有特許権の取扱いについて以下のルールを定めています。このルールが、時としてオープンイノベーションの足かせになることがあります。
| 行為 | ルール | ビジネス上の影響 |
|---|---|---|
| 自身の実施 | 各共有者が単独で自由に実施できる(第73条第2項。ただし、契約で別段の定めをすることで、実施条件(例:ロイヤリティ支払い、事前同意要件)を追加可能。) | 自社製品の製造・販売は可能。 |
| 第三者へのライセンス(通常実施権の許諾) | 他の共有者全員の同意が必要 | パートナー企業に製造を委託したり、技術をライセンスアウトしたりする際に、共有者の同意が得られないと事業展開ができない。 |
| 権利の譲渡、持分の放棄 | 他の共有者全員の同意が必要 | 事業再編などで権利を他社に売却したい場合でも、共有者の同意がなければ不可能。 |
※表は画像化推奨(印刷/アクセシビリティ対応)。詳細は本文参照。

なるほど、自分たちで使う分には問題ないけど、ビジネスを広げようとすると他の共有者の許可がいるのか…これは契約で事前に決めておかないと、後で揉めそうだな。
まさにこの「同意要件」が、共有特許権の「塩漬け」リスクの正体です。共同研究パートナーが将来競合になったり、連絡が取れなくなったりした場合、成果の活用が完全にストップしてしまう可能性があります。
ただし、これらのルールは契約による別段の定め(特約)で変更可能です。例えば、「第三者へのライセンスは、相手方の合理的な理由なき反対がない限り可能とする」といった条項を設けることで、運用の自由度を高めることができます。
成果物の取扱い合意(産学官連携・モデル契約)

こうした共有特許権のリスクを回避し、成果を円滑に事業化するため、経済産業省や特許庁はモデル契約書を公開しています。特に、特許庁の「大学等向け共同研究開発契約書モデル」(Ver.2.2-2025年改訂版)は、成果の帰属パターンを複数提示しており、民間企業同士の契約においても非常に参考になります(出典:特許庁、オープンイノベーションポータルサイト、2025年)。
一般的な帰属パターンには、以下のようなものがあります。
- 甲単独帰属型: 成果はすべて甲(例:費用を多く負担する企業)に帰属させる。乙(大学など)には実施権を与える。
- 共有型(持分均等): 成果は甲乙の共有とし、持分は貢献度によらず50:50とする。運用の手間を省くために採用される。
- 発明者主義型(貢献度に応じる): 各発明を生み出した研究者の所属組織が権利を持つ。貢献度に応じて持分を決定する。
| (記載例:共有型) 本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権は、甲及び乙の共有とし、その持分は甲50%、乙50%とする。甲又は乙は、相手方の書面による事前の同意なくして、自己の持分を第三者に譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定してはならない。 |
※表は画像化推奨(印刷/アクセシビリティ対応)。詳細は本文参照。
どのパターンを選択するかは、研究の性質、費用負担、当事者の役割、将来の事業戦略などを総合的に考慮して決定する必要があります。
トラブル予防のための実務ポイント:NDAとライセンスオプション
契約書で知財の帰属を定めるだけでなく、研究開発のプロセス全体を通じて情報を保護し、成果活用の柔軟性を確保する仕組みも重要です。
秘密保持の補完(不正競争防止法+NDA)

共同研究では、開始前からお互いの重要な技術情報(ノウハウ)を開示し合う場面が多くあります。これらの情報は、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護される可能性がありますが、そのためには「秘密管理性」(情報が秘密として管理されていること)などの要件を満たす必要があります(出典:不正競争防止法第2条)。
この要件を確実に満たし、情報保護を徹底するために不可欠なのが秘密保持契約(NDA)です。NDAは共同研究契約の本体とは別に、交渉段階や研究開始前に締結します。この際、秘密の定義を過度に広げたり、相手方の事業活動を不当に制限するような秘密管理条項を設けると、独占禁止法上の「不公正な取引方法」に該当するおそれがあるため、合理的な範囲内での秘密保持に留める必要があります。
**【Point】**
NDAは共同研究契約の本体とは別に、交渉段階や研究開始前に締結します。これにより、どの情報が秘密であり、どのような目的でのみ使用が許され、いつ返還・破棄されるのかといったルールが明確になり、万一の情報漏洩時の法的根拠となります。
共同研究開発契約の中にも秘密保持条項は含まれますが、研究開始前の情報交換もカバーするために、早い段階でNDAを締結しておくことが鉄則です。
ライセンス条項の設計と曖昧さリスク

研究成果をどちらか一方の当事者が単独で所有し、もう一方がその成果を利用したい場合、「ライセンス(実施権)」の取扱いを定めておきます。
特に、大学との共同研究でよく用いられるのが「オプション権」です。
- オプション権とは?: 研究成果を知財化した際に、企業側がその知財を優先的にライセンスしてもらう権利(選択権)のこと。
- メリット:
- 企業側: 研究成果が出た段階で、事業化の可能性を見極めてからライセンス契約に進むか判断できる。
- 大学側: 企業による事業化の道筋を確保しつつ、もし企業が権利を行使しない場合は、他の企業へライセンスする道も残せる。
ただし、オプション権の契約条項が曖昧だと、かえって紛争の原因になります。
- オプション権の行使期間はいつまでか?
- ライセンス料(ロイヤリティ)の算定基準はどうするか?
- 独占的なライセンスか、非独占的なライセンスか?
これらの点を具体的に定めておかないと、「ライセンス料の交渉がまとまらず、権利行使できない」といった事態に陥りかねません。モデル契約などを参考に、できるだけ具体的な条件を盛り込むべきです。
産学官連携ガイドライン活用:成功事例と注意点
共同研究開発契約、特に産学連携における知財の取扱いについては、国が様々なガイドラインやモデル契約を提示しています。これらを活用することが、成功への近道です。
文科省・JPOモデル契約のポイント

前述の通り、文部科学省や特許庁(JPO)は、産学官連携を円滑に進めるためのガイドラインやモデル契約書を公開しています。これらは大学との共同研究を想定していますが、共同研究の知財管理に関する基本的な考え方は、民間企業同士の契約においても参考価値が高く、その考え方を応用することで、民間企業同士の契約にも大いに役立てられます。
【活用のポイント】
- 知財帰属の多様な選択肢を学ぶ: 単純な共有だけでなく、単獨帰属+ライセンス、貢献度に応じた持分設定など、様々なパターンを知ることで、自社の状況に最適なスキームを検討できます。
- 標準的な条項を知る: 秘密保持、成果の公表、権利の不行使など、知財関連で盛り込むべき標準的な条項を網羅的に確認できます。
- 交渉の土台として使う: 「特許庁のモデル契約ではこうなっています」と提示することで、一方的に不利な契約を結ばされるリスクを減らし、公平な交渉の出発点とすることができます。
これらの資料は各省庁のウェブサイトから無料で入手可能ですので、契約実務に携わる方は一度目を通しておくことを強く推奨します。
改正経過と最新トレンド(2023年特許法改正)

特許法は社会情勢の変化に合わせて改正が重ねられています。近年のトレンドとして、オープンイノベーションを促進する方向での見直しが進んでいます。
例えば、2021年に改正(令和3年法律第42号)され、2023年(令和5年)に施行された改正特許法では、主に共有特許権に関する一部の手続き(共有出願手続簡素化)が簡素化されるなど、共有者の負担を軽減する措置が講じられました(出典:特許法 第38条・第73条、令和3年法律第42号による改正、令和5年施行)。
しかし、このような法改正があったとしても、共有者間の基本的な権利義務関係(例:ライセンス許諾には全員の同意が必要)が変わるわけではありません。法改正の動向を注視しつつも、その根幹にあるのは当事者間の合意であるという原則を忘れないことが重要です。
契約締結時のチェックリストと相談先
最後に、共同研究開発契約を締結する際に最低限確認すべき項目をチェックリストとしてまとめます。
主要条項の明記必須項目

| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| ☐ 研究開発の目的・範囲 | 何をゴールとする研究か、どこまでの範囲を対象とするかが明確か? |
| ☐ 役割分担と費用負担 | 各当事者が担当する業務と、研究にかかる費用の負担割合が具体的か? |
| ☐ 秘密情報の定義と管理 | どの情報が秘密で、どのように管理するかが定められているか?NDAは締結済みか? |
| ☐ バックグラウンドIPの特定 | 研究開始前から各当事者が保有している知財(バックグラウンドIP)の権利関係と利用条件は明確か? |
| ☐ 成果(フォアグラウンドIP)の帰属 | 研究から生まれた知財(フォアグラウンドIP)は誰に帰属するか?(単独、共有、貢献度など) |
| ☐ 共有時の持分と運用ルール | 共有の場合、持分割合は明確か?ライセンスや譲渡の際のルールは特約で定めているか? |
| ☐ 成果の実施・ライセンス | 成果を利用する際の条件(ライセンス料、独占/非独占など)は具体的か?オプション権の定めは明確か? |
| ☐ 成果の公表 | 論文発表など、成果を公表する際のルール(事前同意の要否、時期など)は定められているか? |
| ☐ 契約期間と終了後の措置 | 契約が終了した後も、守秘義務や成果の利用権はどうなるかが明确か?現契約条項が最優先適用される。 |
※表は画像化推奨(印刷/アクセシビリティ対応)。詳細は本文参照。
このチェックリストはあくまで一般的なものです。実際の契約では、より詳細な項目について弁護士や弁理士などの専門家と共にレビューすることが不可欠です。状況によって異なるため、専門家に相談することを強くお勧めします。
JPOガイドライン相談の有効性

自社だけでの契約交渉やレビューに不安がある場合、公的な相談窓口を活用するのも有効な手段です。特許庁(JPO)は、オープンイノベーションや知財戦略に関する相談窓口を設けており、契約に関する一般的なアドバイスを受けることができます。JPOオープンイノベーションポータルサイトの相談窓口では、共同研究開発契約の知財帰属に関する相談も可能です(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/)。
こうした公的機関の助言を参考にしながら、最終的には自社の事業戦略に合致した形で、専門家と共に契約書を作り上げていくことが、トラブルを未然に防ぎ、オープンイノベーションを真の成功に導く鍵となります。
まとめ
本記事では、共同研究開発契約における知的財産権の帰属と成果の取扱いについて、以下の点を中心に解説しました。
- 契約の重要性: 共同研究開発契約は、オープンイノベーションの成功を左右する基盤であり、特に知財帰属のルールを明确化することが紛争予防に直結します。
- 法の基本原則: 特許法上の「職務発明」や著作権法上の「職務著作」のルールを理解しつつも、共同研究では当事者間の契約が優先されることを認識する必要があります。
- 共有特許権のリスク: 複数の当事者で権利を共有する場合、特許法第73条により権利活用に制約が生じるため、契約で柔軟な運用ルール(特約)を定めることが不可欠です。
- 実務上の予防策: 研究開始前のNDA締結や、成果活用の柔軟性を確保するライセンスオプション条項の設計が重要です。
- モデル契約の活用: 特許庁などが公開するモデル契約は、交渉の土台や条項の抜け漏れチェックに非常に有用であり、積極的に活用すべきです。
共同研究開発は、単独では成し得ない大きなイノベーションを生み出す可能性を秘めています。その可能性を最大限に引き出すためにも、本記事で解説したポイントを踏まえ、戦略的かつ慎重な契約マネジメントを実践してください。
免責事項
本記事は、共同研究開発契約に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスを提供するものではありません。契約書の作成やレビュー、具体的な法的判断にあたっては、必ず弁護士や弁理士などの専門家にご相談ください。また、法令やガイドラインは改正される可能性があるため、常に最新の情報をご確認ください。
参考資料

- 特許法(最終改正:令和三年法律第六十三号) – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
- 著作権法(最終改正:令和五年法律第三十三号) – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
- 不正競争防止法(最終改正:令和五年法律第五十一号) – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000047
- 民法(最終改正:令和三年法律第七十五号) – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 知的財産推進計画2025(内閣官房、2025年3月) – https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku.pdf
- 大学等における「知」のマネジメントと活用のためのガイドライン(INPIT、2021年)
- 「大学・事業会社」間の共同研究開発契約書(Ver.2.2-2025年改訂版・逐条解説付き)(特許庁、2025年) – https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/uni-com-v2_1-kyoudou_chikujouari.pdf
- 研究開発型スタートアップと事業会社の連携のためのガイドライン(追補版)(経済産業省、2020年)

植野洋平 |弁護士(第二東京弁護士会)
検察庁やベンチャー企業を経て2018年より上場企業で勤務し、法務部長・IR部長やコーポレート本部の責任者を経て、2023年より執行役員として広報・IR・コーポレートブランディング含めたグループコーポレートを管掌。並行して、今までの経験を活かし法務を中心に企業の課題を解決したいと考え、2021年に植野法律事務所を開所。