景品表示法の概要と近時の改正:企業が押さえておきたい最新ポイント
お役立ち記事一覧に戻る景品表示法は、事業者が商品やサービスを宣伝する際に消費者を誤認させるような表示(不当表示)や、過度な景品(不当景品類)を提供することを防ぐために制定された法律です。ここ数年で規制の強化や改正が相次ぎ、企業は最新の動向を把握して実務に生かすことが求められています。
特に、インターネット広告やSNSを活用したマーケティングの普及により、景品表示法のリスクは日々多様化しています。消費者庁による摘発事例も増加しており、誤った表示や無自覚なステルスマーケティングは企業にとって大きな打撃になりかねません。
本記事では、景品表示法の概要から主要規制、近時の改正ポイントまでを体系的に解説します。法改正の施行スケジュールや実務対応の注意点を整理し、企業のコンプライアンス水準を高めるためのヒントを提供します。
| 景品表示法第一条 商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 |
不当表示
不当表示とは
| 景品表示法第五条柱書 ①事業者は、➁自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する③表示をしてはならない。 |
①事業者であること
景品表示法の規制対象になるのは「事業者」であり、「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」と規定されています(景品表示法第2条第1項)。また、営利を目的としない協同組合、学校法人等や地方公共団体その他の公的機関等であっても、事業を行っていると認められる場合には、事業者に該当します。
→幅広い事業者が規制対象になる。
➁供給主体性があること
当該事業者が、問題となる表示に係る商品・役務を「供給」しているといえることが必要です。例えばあるメーカーの商品の広告を作成する広告代理店は、商品を供給しないため規制対象に当たりません。また、供給主体性は商品等の提供・流通の実態をみて実質的に判断され、例えば、フランチャイズの本部が行う表示等に関し、本部自体は消費者との間で当該商品等の売買契約の当事者ではない場合でも、この要件を満たすと判断された処分事例があります。
③表示主体性があること
当該事業者が不当表示をしたといえることが必要です。表示主体性は、「表示内容の決定に関与した事業者」に認められます。
| 「表示内容の決定に関与した事業者」とは(表示の定義 Q&A問2) |
|---|
| ■自らもしくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者 ■他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者(他の事業者が決定したあるいは決定する表示内容についてその事業者から説明を受けてこれを了承した事業者 ■他の事業者にその決定を委ねた事業者 (自己が表示内容を決定することができるにもかかわらず他の事業者に表示内容の決定を任せた事業者) |
(2) 表示の例(告示「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
| ●チラシ・パンフレット、カタログ、ダイレクトメール ●容器、パッケージ、ラベル ●新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM ●ディスプレイ(陳列)、実演広告 ●セールストーク(訪問・電話) ●ポスター、看板 ●SNSの投稿、口コミ、メール、アフィリエイト広告 ●インターネット上の広告、商品等のプレスリリース |

口コミ、セールストークも入るなど、表示の範囲は広くとらえられていますので、慎重な対応が必要ですね。
(3) 不当表示の種類(景表法第五条各号)
ア. 優良誤認表示の禁止
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
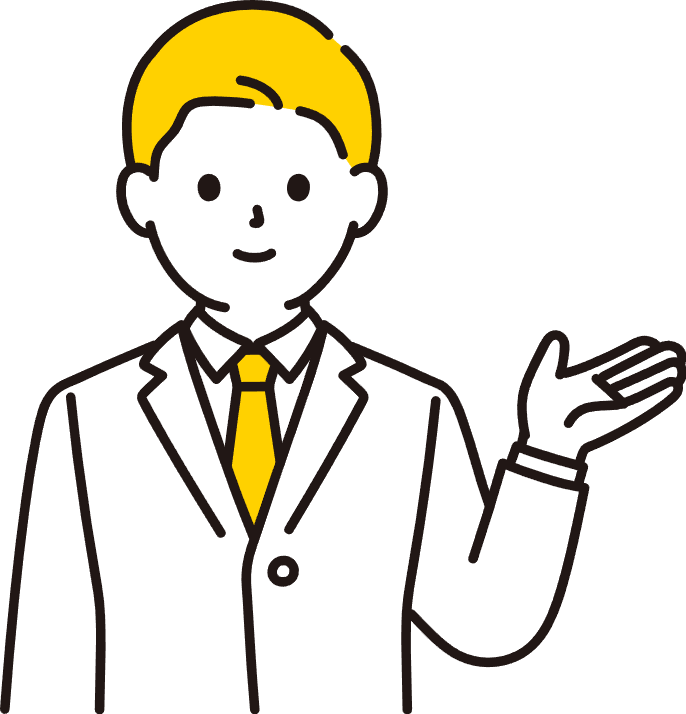
いい品質(企画、内容)だと消費者に思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです。
| 例:果実ジュース…実際にはほとんど果汁が入っていないにも関わらず、あたかも大部分が果汁のジュースであるかのように表示されたジュース。 |
イ. 有利誤認表示の禁止
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を有利誤認表示として禁止しています。

お得な商品だと消費者に思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです。
| 例:家電量販店の店頭価格について、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた。 |
ウ. その他誤認される恐れのある表示の禁止(告示にて規制)
6つの告示があったところ、7つ目が追加されました(令和5年3月28日内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」)。
| ●無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示 ●商品の原産国に関する不当な表示 ●消費者信用の融資費用に関する不当な表示 ●不動産のおとり広告に関する不当な表示 ●おとり広告に関する不当な表示 ●有料老人ホームに関する不当な表示 ●一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 NEW |
2. 不当景品類
景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制しています。
(1) 不当景品類とは
| 景品表示法第二条3項 この法律で「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の➁取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の③経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 |
➀顧客誘引性
提供者の主観的意図やその企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引のための 手段になっているかどうかによって判断します(「景品類等の指定の告示の運用基準について」1(1))。親睦、儀礼、謝恩等のため、自己の供給する商品の容器の回収促進のため又は自己の供給する商品に関する市場調査のアンケート用紙の回収促進のための金品の提供であっても、「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められることがあります。また、新たな顧客の誘引に限らず、取引の継続又は取引量の増大を誘引するための手段も、「顧客を誘引するための手段」に含まれます。
➁取引に付随して
商品の購入など取引を条件とする場合よりも広く、「取引に関連して」との意味であると考えられており、来店が条件となるなど事業者側から商品の購入の働きかけを行いうる場合は取引付随性があるとされています。一方、ウェブサイト上の広告については、消費者がこれを閲覧するかどうかは自由であって、取引対象商品の広告が掲載されているサイトから他のサイトに自由に移動できることから、通常、取引付随性はないとされています。
③経済上の利益
| ● 物品及び土地、建物その他の工作物 ● 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び 公社債、株券、商品券その他の有価証券 ● きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) ● 便益、労務その他の役務 ※値引き、アフターサービス等は除く。 |
事業者が、そのための特段の出費を要しないで提供できる物品や市販されていない物品等であっても、提供を受ける者の側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは、「経済上の利益」に含まれます。ただし、経済的対価を支払って取得すると認められないもの(例 表彰状、表彰盾、表彰バッジ、トロフィー等のように相手方の名誉を表するもの)は、「経済上の利益」に含まれません。
(2)不当景品類の分類(告示)
ア. 一般懸賞(内閣府告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)
商品・サービスの利用者に対する、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって提供する景品類のこと
| 懸賞による 取引価額 | 一般懸賞における景品類の限度額 | |
| 最高額 | 総額 | |
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | |
イ. 共同懸賞
商品・サービスの利用者に対する、一定の地域や業界の事業者が共同して提供する景品類のこと
| 共同懸賞における景品類の限度額 | |
| 最高額 | 総額 |
| 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
ウ. 総付(内閣府告示「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)
懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく提供される景品類のこと
| 総付景品の限度額 | |
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の2/10 |
景品類規制について、消費者庁は近年違反事例の摘発や改善に向けた取り組みは活発に行われておらず、規制内容も大きな変更がされていないため、現在のビジネスに適用して適法違法を判断することが難しくなっています。
3. 違反への対応
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施し、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を付与した上で、違反行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行います(景品表示法第7条)。
また、消費者庁は、違反行為の中でも、課徴金対象行為(優良誤認表示又は有利誤認表示をする行為)をした事業者に対しては、事業者に弁明の機会を付与した上で、金銭的な不利益を課す「課徴金納付命令」を行います(景品表示法第8条)。
最近の改正について
1. アフィリエイト広告
(1)背景
アフィリエイト広告とは、ウェブサイト運営者が広告主の商品等を紹介し、その紹介を経由して購入や申し込みが行われた際に報酬を得る仕組みです。商品等の販売者ではないアフィリエイターが広告を作成・掲載していることから、販売業者の広告に対する責任意識が希薄になりがちであり、広告内容のコントロールが行き届きにくくります。また、成果報酬型の仕組みであるため、アフィリエイターが虚偽・誇大な広告を作成する傾向があります。
(2)概要
内閣府告示「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」を改正し、指針にアフィリエイト広告についての記述が追加されました。
アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーに供給主体性が認められないことや、広告主に表示主体性が認められるかが明確でないため、誰に景表法が適用されるか議論されていたところ、令和3年2月の検討会の報告書で、表示主体性は広告主に適用されうることが明確化されました。
一方でアフィリエイト広告そのものが問題のある広告手法というわけではなく、規制拡大は委縮効果を招く可能性があること等から、アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーは責任主体として位置付けられませんでした(「アフィリエイト広告報告書」III I (2)ア)。
他方、アフィリエイター等は特定商取引に関する法律では「役務提供事業者」が、薬機法では「何人も」規制の対象となります。
2. ステマ規制
表示関係の新たな指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が追加されました。
(1)背景
ステルスマーケティングとは、事業者が自らの広告であることを隠して行う広告をいいます。消費者は、事業者自身が関与している広告であると認識していれば慎重な姿勢をとりますが、事業者とは無関係の第三者の評価であるかのように装われていれば、そのように身構える意識が働かないため表示を信じやすくなります。
近年SNSなどのデジタル広告市場が拡大し、これまでの表示広告を独占してきたマスメディア業界による自主規制も及ばなくなっています。
(2)要件
| 景品表示法指定告示7 「一般消費者が①事業者の表示であることを➁判別することが困難であること」 |
(消費者庁長官決定「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準」)
①広告主が表示したといえること
外形上第三者の表示のように見えるものが事業者の表示に該当するとされるのは、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合であり、※客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合をいうとされています。(運用基準 第2. 2. (1))
| ※客観的な状況に基づき とは ● 事業者と第三者の間の表示内容に関する情報のやり取りの有無 ● 表示内容に関する依頼・指示の有無 ● 事業者から第三者への対価の提供の有無 ● 事業者と第三者の関係性(表示内容の決定に関与できる程度の関係があるのか |
② ①の場合、広告主の表示であることが不明瞭なこと(運用基準 第3. 1. (1),(2))
一般消費者から見て、事業者の表示であることを判別することが困難であるか否かの判断は、事業者の表示であることが明瞭となっているか否か、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないか否かを表示内容全体から判断する。
| 広告主の表示であることが不明瞭な例 ● 事業者の表示であることが全く記載されていない場合 ● 事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合 ● 冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、事業者の表示である旨が分かりにくい表示である場合 ● 動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合 |
表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。
(3)今後の対応
具体的な行動指針として、ステマ告示運用基準が公表されていますが、これについても抽象的で実務的な指針としては十分でなく、事業者が実務対応に苦慮している実態があります。
例えばインフルエンサーに依頼してSNSに自社製品の感想を投稿してもらうとしても、必ずしもステマ規制の要件を充足するとは限らないとしているものの、その表示内容について明示的な依頼や指示がなくても事業者の表示に該当する場合があるとされていることもあり、実務的には「広告」「PR」等の文言を表示すること等によって事業者の表示であることを明瞭にする必要があります。

広告と記載したとしても、第三者の感想である旨を記載しないような注意も必要です。
ステマ広告の効果を高めるためにグレーゾーンを狙うよりも、積極的にプロモーション活動の一環であることを明確にした方が望ましいでしょう。
企業が注意すべき実務対応とコンプライアンス
法令を遵守しつつ消費者の信頼を獲得するためには、表示物の確認体制や内部教育の充実など総合的な取り組みが求められます。
景品表示法への対応は、一度ルールを策定すれば終わりではなく、継続的な見直しと運用が必要です。商品アップデートや価格変更の際には、伴う広告表現の修正や再チェックが必須となります。
社内の関連部門(マーケティングや法務、品質管理など)が連携し、キャンペーンを実施する際に十分な根拠資料をそろえて広告を作成することが肝心です。特に変更や追加があった時点で、更新情報を社内に共有して周知徹底する運用体制が重要となります。
また、万が一、消費者や行政から指摘を受けた際には、速やかに改善策を打ち出せるよう、ルールや手続きをあらかじめ設定しておくと企業リスクを最小限にとどめられます。
広告表示の事前チェック体制づくり
広告を公開する前に法務担当や外部専門家が表示内容を点検する仕組みを構築することは、違反リスクを大幅に下げるうえで不可欠です。特に優良誤認や有利誤認のおそれがある表現については、データや根拠書類を整備し、必要に応じて修正案を検討します。
チェック体制が無い場合、部門ごとに異なる基準で広告を作成してしまい、不当表示が見逃されるおそれがあります。組織横断的に情報共有するための会議やシステムも活用すると、リスクを抑える効果が高まります。
実務では契約書や業務フローの段階で、景品表示法のチェックポイントを明示し、承認フローに組み込んでおくとスムーズに確認できるようになります。
違反リスク低減に向けた教育・マニュアル整備
広告担当者や企画担当者が、景品表示法の基礎知識を常にアップデートできる環境を整えることは重要です。新入社員や異動してきた社員にも、研修やセミナーを通じて対応のポイントを周知していくと良いでしょう。
具体的なマニュアルを用意し、よくある誤認表示の事例や法令違反リスクをわかりやすくまとめることで、トラブルを未然に防いだり、問題が起きた際の初動対応が迅速化します。
また、社内SNSや掲示板などを活用して、実務で発生した課題や疑問を共有する仕組みを作ると、全員が常に景品表示法を意識した行動を取りやすくなります。
まとめ・総括
絶えず改正や運用強化が進む景品表示法を適切に理解し、企業活動に落とし込むことは、長期的視点からの信頼獲得とリスク回避において欠かせません。
景品表示法は消費者の選択を守るために設けられた法律であり、企業にとってはコンプライアンス上の大きなハードルにもなり得ます。違反が発覚すると多額の課徴金やブランドイメージの損失を招きかねないため、最新の法令改正情報やガイドラインをキャッチアップする努力が必要です。
特にインターネット広告やSNS上での宣伝活動は規制対象となる範囲が広がっており、ステルスマーケティングやアフィリエイト広告など、新しい手法にまで監視の目が行き届いています。企業は法務担当や専門家と連携し、広告表示の根拠となるデータや分析結果を日頃から整理する体制を整備すると効果的です。
これからも改正が続く可能性が高いため、内部研修やマニュアル整備によって社員全員の意識を高め、適切なマネージメントを行うことで、社会に信頼される企業として成長していくことが求められます。
